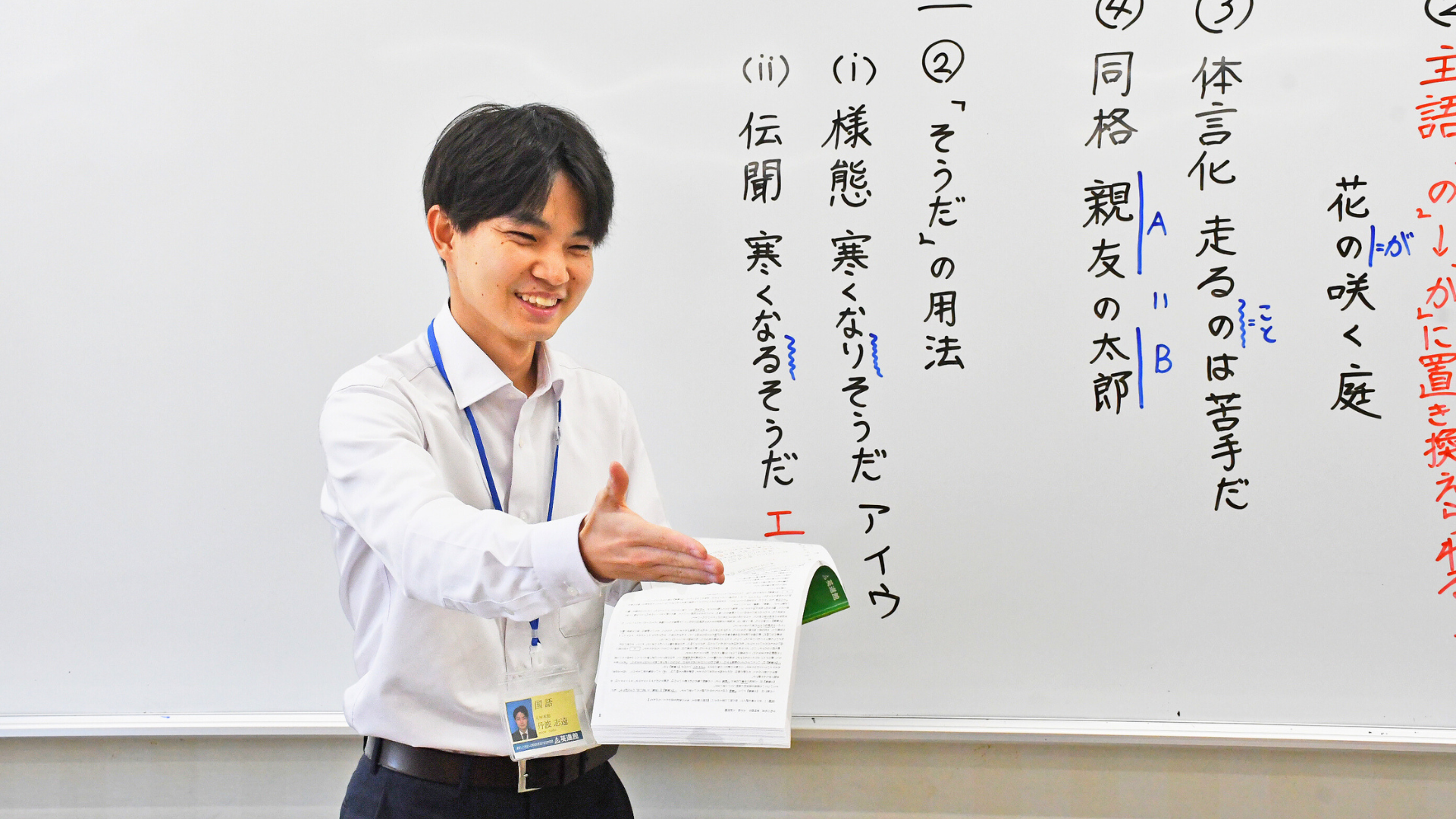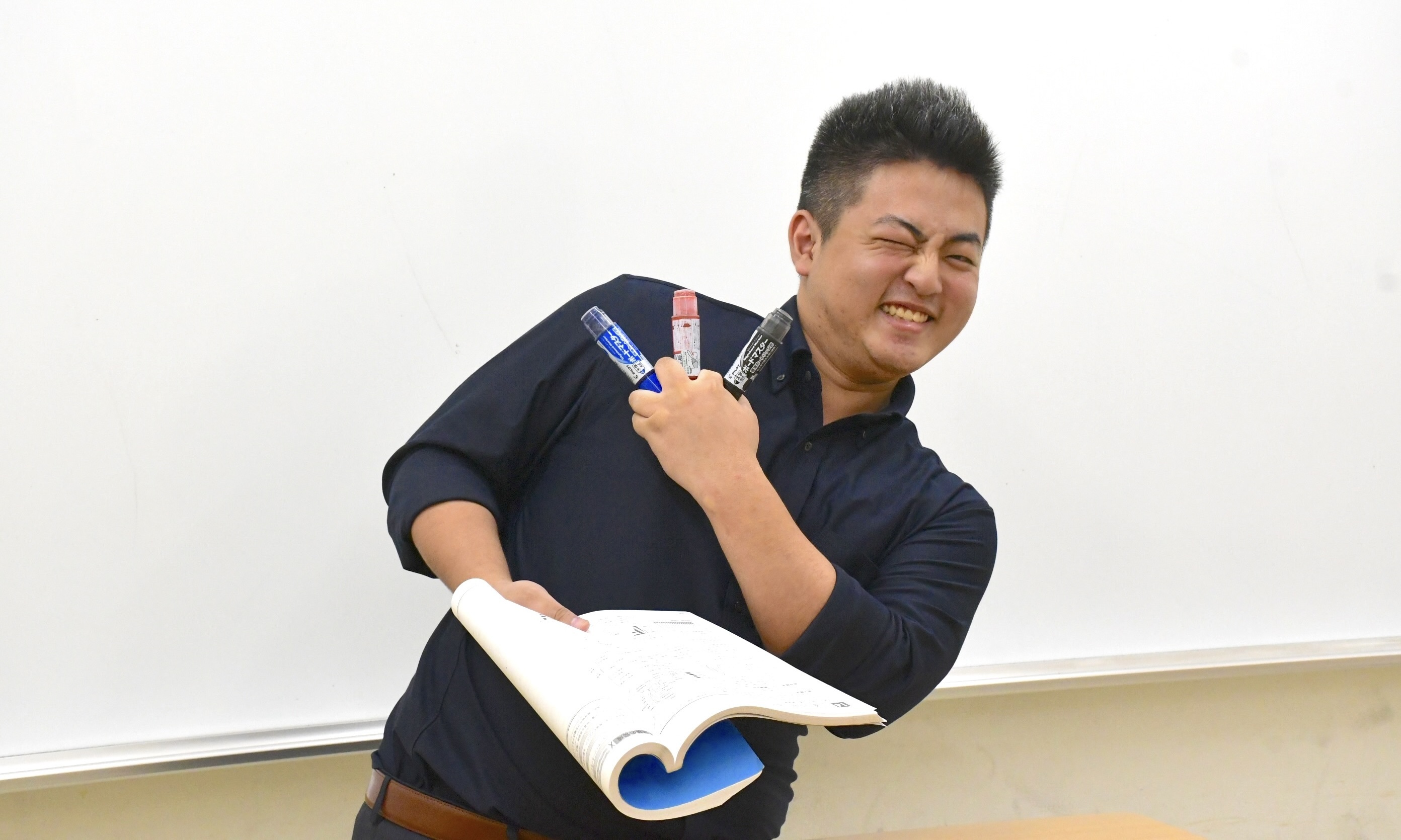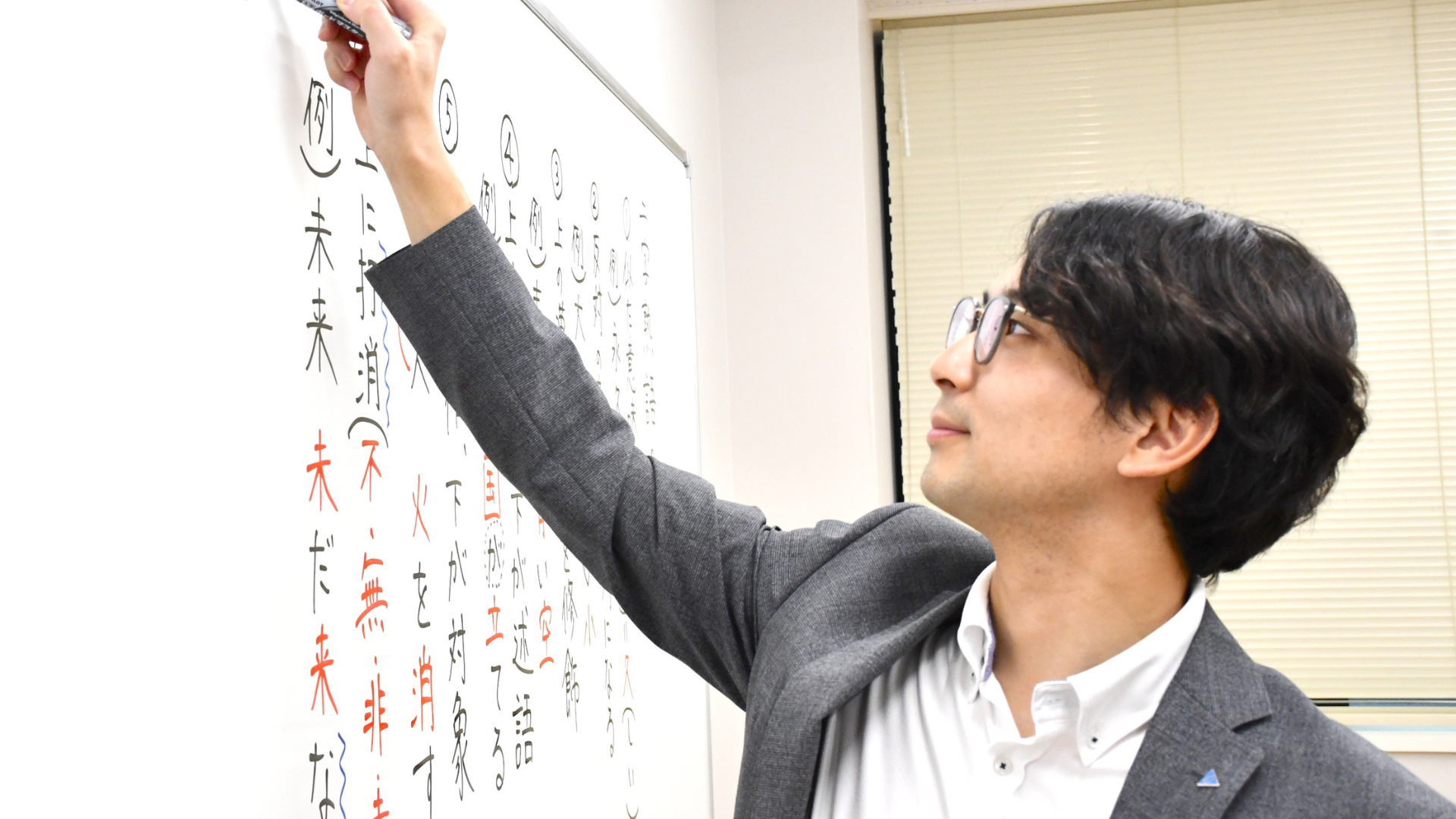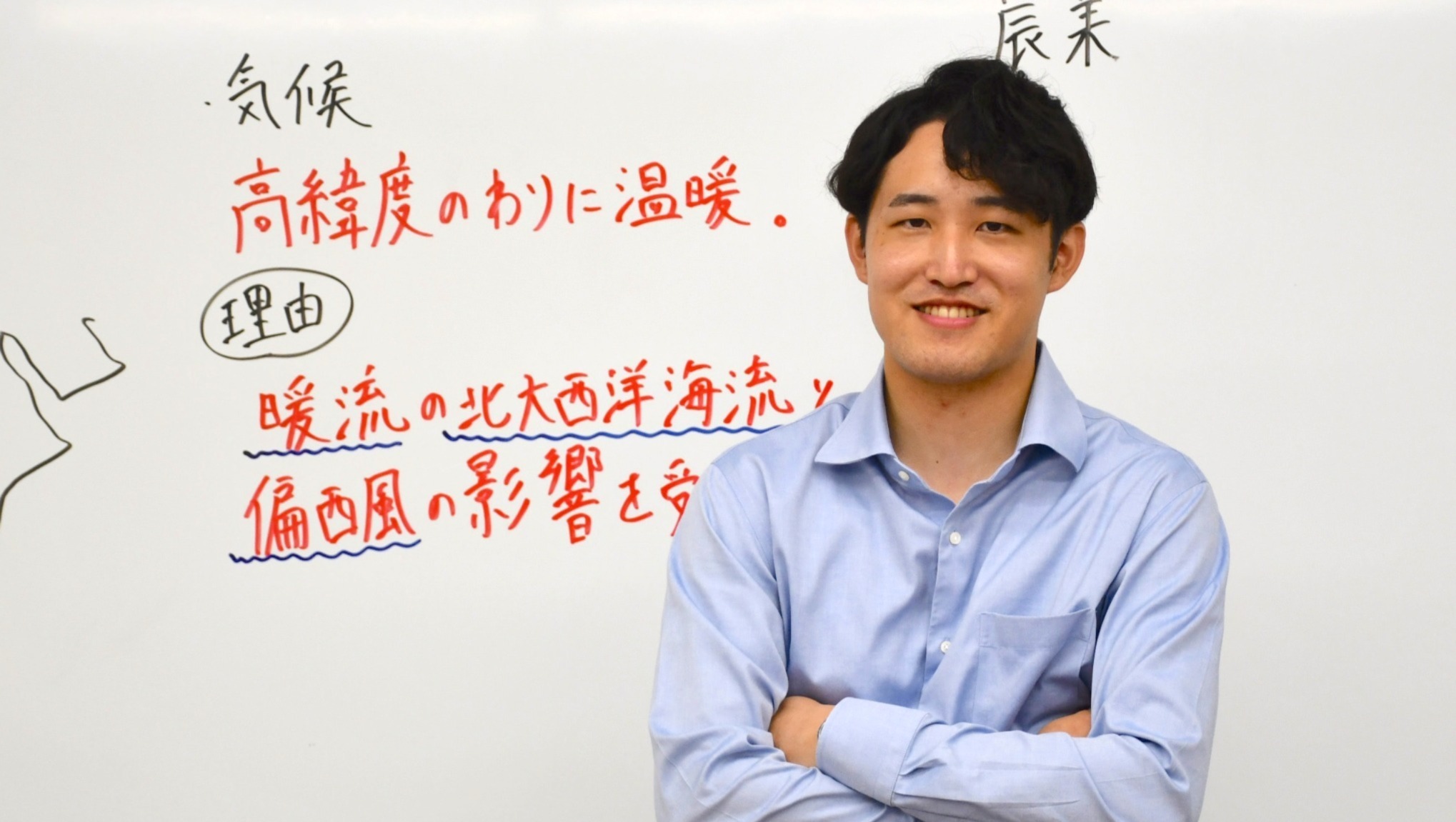人間らしい共感力が教育を支える/個別指導 山岡 雅明
2025/07/23
「共感力」と「信頼関係」を何よりも大切に。
生徒が困難に直面したときこそ、一番近くで支える存在でありたい。
PROFILE

山岡 雅明
2021年4月新卒入社
鹿児島大学出身
個別指導担当スタッフ
多様な教育観が息づく環境に惹かれて
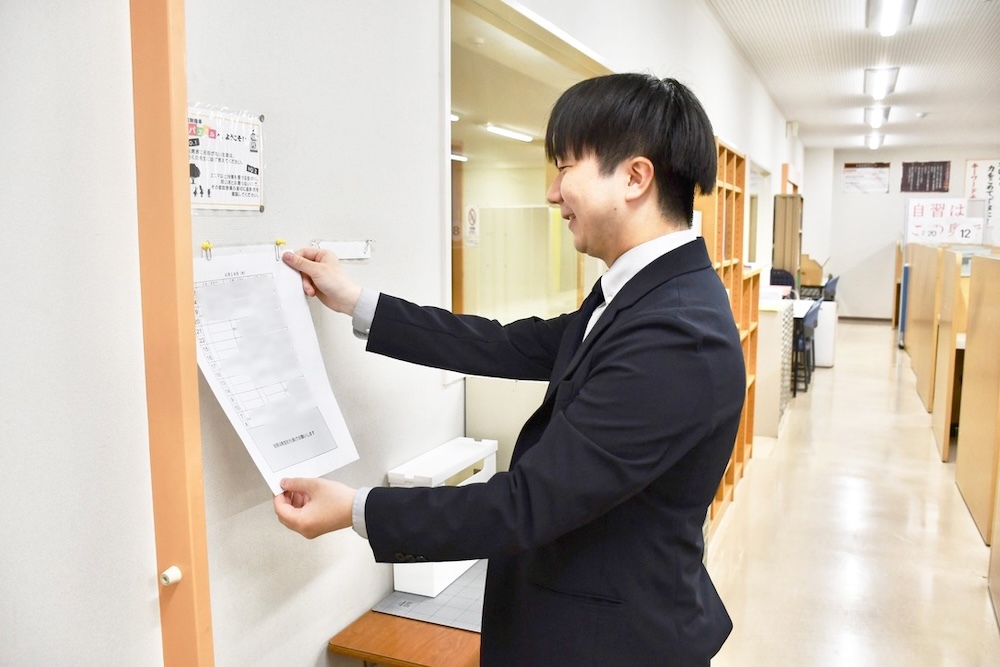
英進館との出会いは、教員を志して教育学部に進んだことが始まりでした。大学3年生になり、就職活動を意識し始めた頃、教育業界の大手企業として英進館の存在を知りました。
地方出身のため、大規模な学習塾の存在は縁遠かったのですが、就職情報サイトで初めて英進館を知り、強く惹かれました。九州最大の規模を誇る英進館なら、多様な教育観を持つ人々と共に働き、その価値観に触れることで自身の感性をより深く磨き上げられると感じたのです。
当時は鹿児島に住んでいたのですが、福岡で行われたインターンシップへ、片道4時間半かけて何度も足を運びました。
大学で教員免許を取得しましたが、私自身は勉強を教えること以上に、生徒や保護者の方々との対話を通じて関係性を築くことに魅力を感じていました。彼らの心身のサポートや、成長を見守る役割こそ、自分のやりたいことだと思えたのです。
そうした意味で、公教育の枠組みにとらわれず、より柔軟な対応が可能な民間教育に大きな可能性を感じ、英進館への入社を決意しました。
実際に働き始めて感じるのは、想像以上に自由度が高く、しがらみのない環境であるということです。生徒と自然体で向き合い、自分らしく働けることに、日々確かな手応えを感じています。
130名の学びを支える統括業務の醍醐味
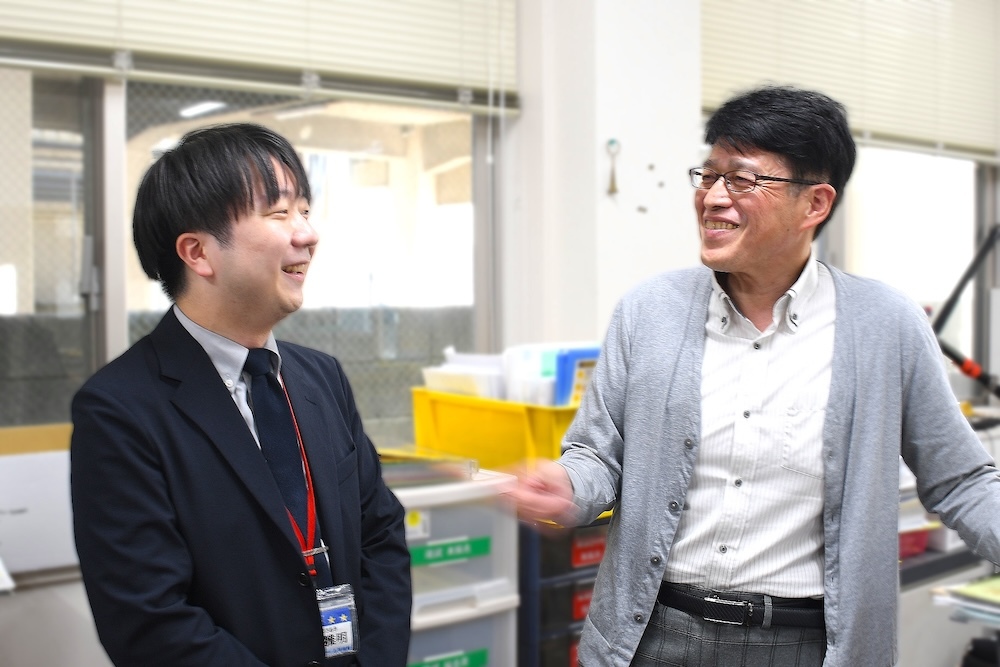
現在私は個別指導部門「パスカル」で、教場全体の統括業務を担っています。個別部門の場合、実際の指導は大学生を中心としたアルバイト講師が担当しますが、社員である私がその円滑な運営・管理に尽力しています。
私が所属する久留米本館は、パスカルの中でも特に規模の大きな教場で、常時130名ほどの生徒が在籍しています。直接授業を受け持つことはありませんが、講師陣のフォローを行いながら、「この生徒にはどのような指導が最適か」といった学習プランを常に検討しています。
もともと「生徒ともっと深く関わりたい」という思いが強く、個別指導に特化した環境は自分に最適だと感じたため、今の職種を選びました。生徒や保護者の方々へのきめ細やかなサポートはもちろん、講師の育成やフォローも重要な責務の一つです。
直接授業は担当しませんが、そのぶん講師陣と密に連携を取りながら、生徒一人ひとりの苦手分野や学習課題を把握する努力を続けています。例えば、定期テストの成績を詳細に分析したり、担当講師から普段の様子をヒアリングしたり、保護者の方からご家庭での学習状況をお聞きしたりと、多角的な情報収集を心がけています。
もちろん全てを完璧に把握するのは難しいですが、ひとつでも多くの「悩み」や「困り事」を拾い上げ、解決に結び付けられるよう、できる限りの努力をしています。
数多くの経験がもたらした確かな成長

最初の配属先は天神本館でした。ここは生徒数が多く、保護者対応も頻繁に求められる多忙な教場でしたが、とても充実した日々をすごせたと思います。個別指導の現場では、生徒一人ひとりの学習内容が異なり、保護者の方々からのご要望も多岐にわたるため、それぞれの状況を把握することに力を注ぎました。
正直なところ、私はいわゆる「マルチタスク」が得意ではなかったため、「この生徒はどんな内容に取り組んでいるのだろう?」「この保護者の方とはどんなお話をしたかな?」といった、情報の整理にはかなり苦労しました。しかし、業務の幅が深くて広いからこそ、多くのことを吸収し、成長できるチャンスだと捉えていました。
この経験は、私にとって貴重な学びの機会となりました。日々の業務を通じて、効率的に情報を整理するスキルや、多様なニーズに対応する力が自然と身についていったと思います。
目の前の生徒や保護者の方々と真摯に向き合うことで、一つひとつの課題を乗り越え、自身の成長を実感できたのです。そのようにいわゆる「場数を踏む」ことによって、徐々に業務に慣れていきました。
やはり経験の積み重ねが、成長への一番の近道だったと実感しています。今では、当時よりも多くの生徒を担当していますが、自然と全体を見渡せるようになり、自分なりに進歩したんだな、と感じています。
困難なときこそ「寄り添う」ことが大切
生徒が志望校に合格したとき、成績が向上したときの喜びは、何にも変えがたいものです。一方、当然ですが、全ての生徒が100%満足のいく結果を得られるわけではありません。
例えば、受験で第一志望校に合格できなかったり、ご家庭で親子関係にすれ違いが生じているとします。こんな時に私が間に入って話を聞き、温かい言葉をかける。そのように、「つまずいている時に寄り添えるかどうか」こそが、自分自身の真価が問われる瞬間だと思っています。
もちろん、望みどおりの結果にならなかった時には悔しい気持ちもあります。それでも、その生徒のこれまでの努力や頑張りを間近で見てきたからこそ、その価値をキチンと言葉にして伝えてあげられるのは自分だけ…そう自らに言い聞かせて日々生徒に接しています。
快適に働ける環境
学習塾という特性上、朝よりも夕方以降~夜の時間帯に比重が置かれた働き方になります。私自身は、学生時代から夜型の生活に慣れていたため、特に負担を感じることはありませんでしたが、もし生活リズムに不安を感じている方がいても、入社後には自然と適応していけるので、大丈夫です。
また、休日もしっかりと確保できるので安心してください。私の定番の過ごし方は、カフェでコーヒーを片手に小説を読むことです。落ち着いた時間を過ごすことで心身ともにリフレッシュしています。
また、うどんが大好物なので、福岡県内のうどん屋巡りも楽しみの一つです。

基本姿勢は「否定しない・押し付けない・傾聴する」
仕事をする上で、私が特に意識していることは大きく3点あります。
まず1点目は「否定しないこと」です。生徒や保護者の方の意見に対して、たとえ内心で異なる意見であったとしても、頭ごなしに否定せず、まずは一度しっかりと受け止めるよう努めています。なぜなら、否定から入ってしまうと、その後の信頼関係構築が困難になると考えているからです。
2点目は「(正論を)押し付けないこと」です。例えば、「テスト前は当然勉強すべきだ」といった正論があったとしても、部活動などの事情で思うように勉強できなかった生徒もいます。そうした状況では、まずその背景や事情を深く理解し、その上で今後の改善策を共に模索するようにしています。
そして3点目は「傾聴すること」です。中学生の頃から人の話を聞くのが好きだったこともあり、相手の言葉に真摯に耳を傾ける姿勢は、これまでずっと大切にしてきました。特に個別指導の現場では、相手の話を丁寧に聞くことが、信頼関係を築くための第一歩であると強く感じています。
特別なことをしているわけではありませんが、この3つの原則を大切にすることで、生徒や保護者の方々にとって「いざという時に頼れる存在」になれたらと願っています。
困った時に思い出してもらえる存在でありたい

性格的に「新しいことにどんどん挑戦したい!」というタイプではありません。どちらかというと保守的で、新しいことに取り組むには相当なエネルギーを要するため、今の自分のスタンスを大切にしたいと考えています。
その上で、私が目指したいのは「困った時に思い出してもらえる」ようになることです。生徒や保護者の方が、学習面で壁にぶつかった時や、何かに悩んでいる時に「ちょっと山岡先生に相談してみようかな」と自然に思ってもらえるような、そんな深い信頼を寄せられる存在でありたいですね。
新たな取り組みを始めることを意識しつつも、今の生徒や保護者の方々との関わり方や姿勢を大切にし、これから出会う一人ひとりと、着実に信頼関係を築いていきたいと考えています。
個別指導で確信した「共感力」の重要性
これから英進館への入社を検討されている方々に、私からぜひお伝えしたいのは「共感力の大切さ」です。勉強に苦手意識を持つ生徒や、不安を抱える保護者の方々の気持ちを深く理解し、寄り添う姿勢は、教育現場において欠かせない力だと確信しています。
私自身は、学生時代に勉強で大きな苦労をした記憶があまりありませんでした。しかし、社会人となり多くの生徒と接する中で、「なぜできないのだろう?」と考えるのではなく「こういう生徒もいるんだ」と受け入れることの大切さを学びました。
個別指導の現場では、生徒の状況や学習レベルは多種多様です。だからこそ、相手の立場に立って物事を深く考える力が、何よりも重要であると痛感しています。
近年、AIの発展は目覚ましいものがありますが、私は「共感力」こそが人間にしか持ち得ない、かけがえのない価値だと思っています。誰かの気持ちに寄り添い、その時々において最適な言葉や関わり方を選ぶ。それはきっと、どんな時代においても求められる力です。
最後に、学生の皆さんにお伝えしたいのは、「大学生活を心ゆくまで楽しんでほしい」ということです。
社会人になると、どうしても時間の使い方や自由度は変化します。将来に不安を感じることもあるかもしれませんが、社会に出てからでも案外なんとかなるものです。だからこそ、今しかできない貴重な経験をたくさん積んでいただきたいです。
英進館は、教育に少しでも興味がある方にとって、大きなやりがいを見つけられる環境だと確信しています。皆さんと共に働けることを楽しみにしています。