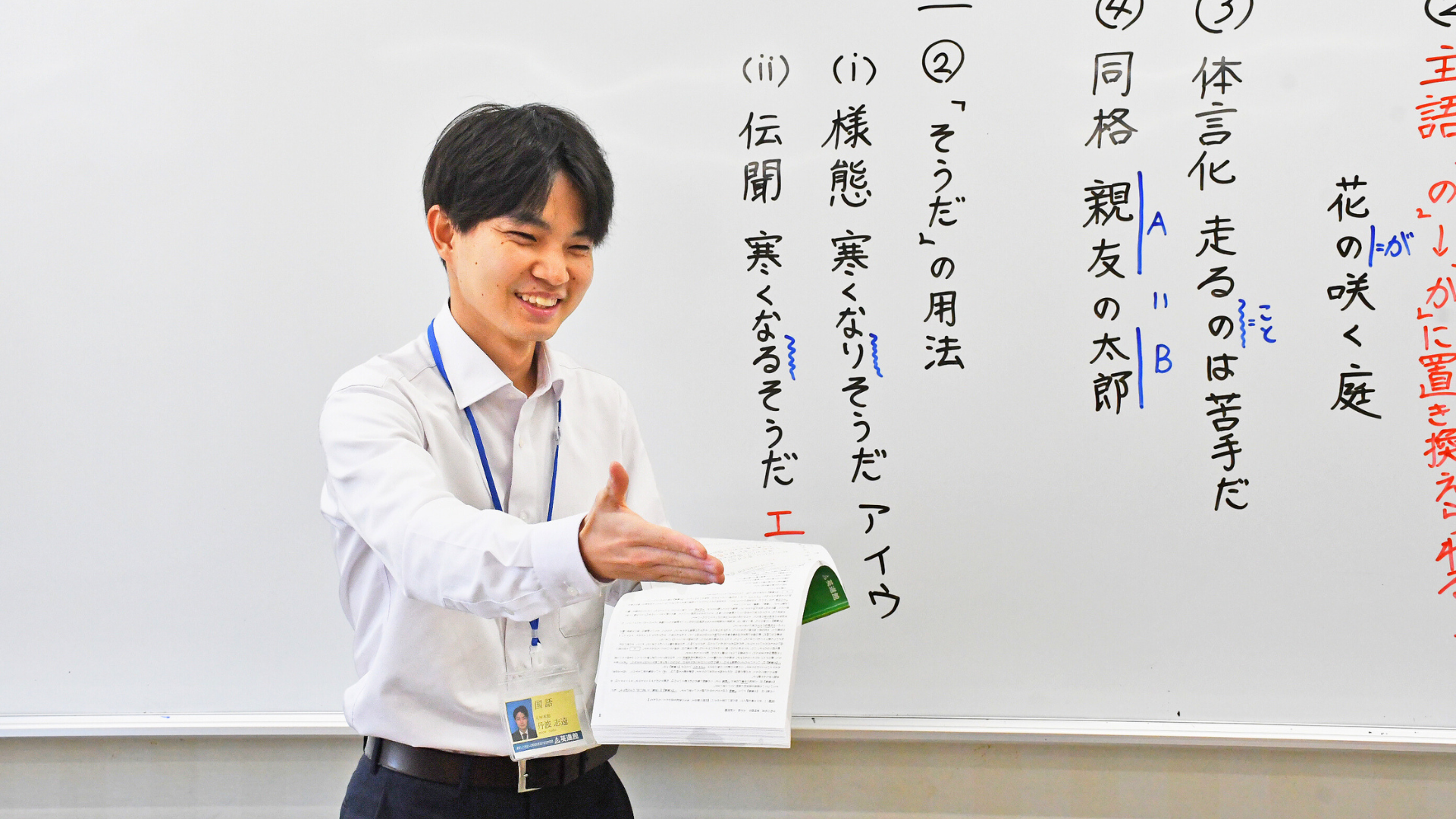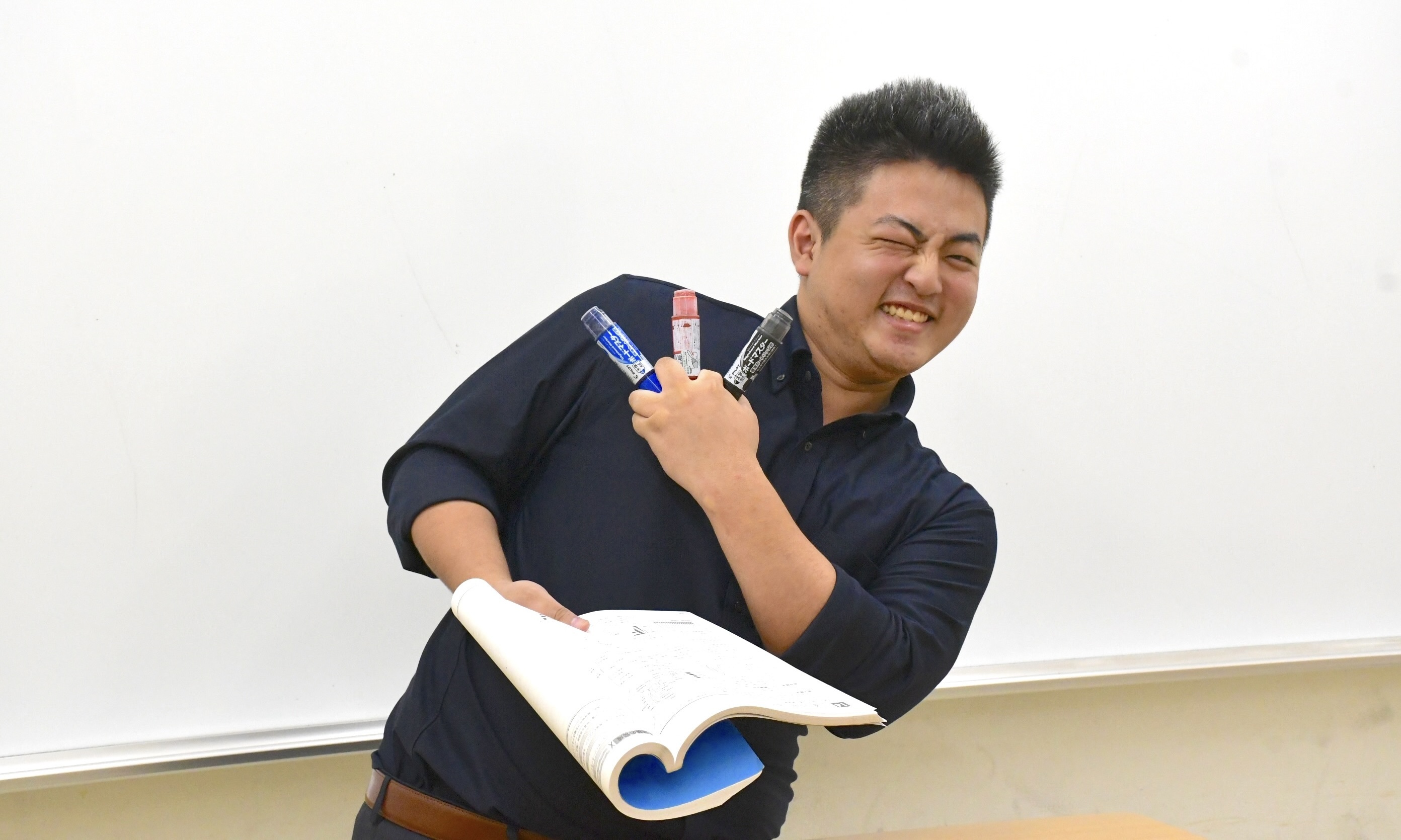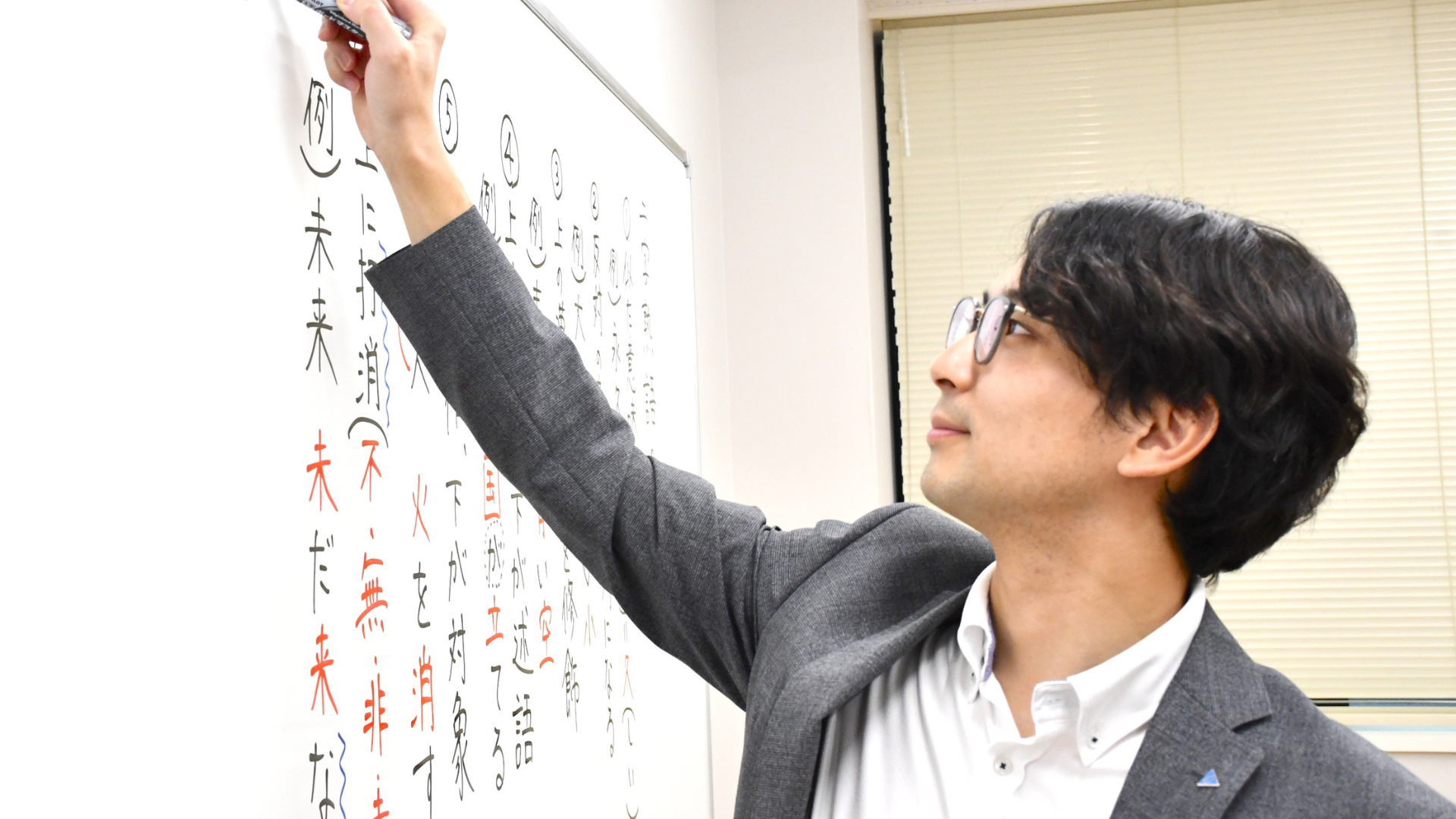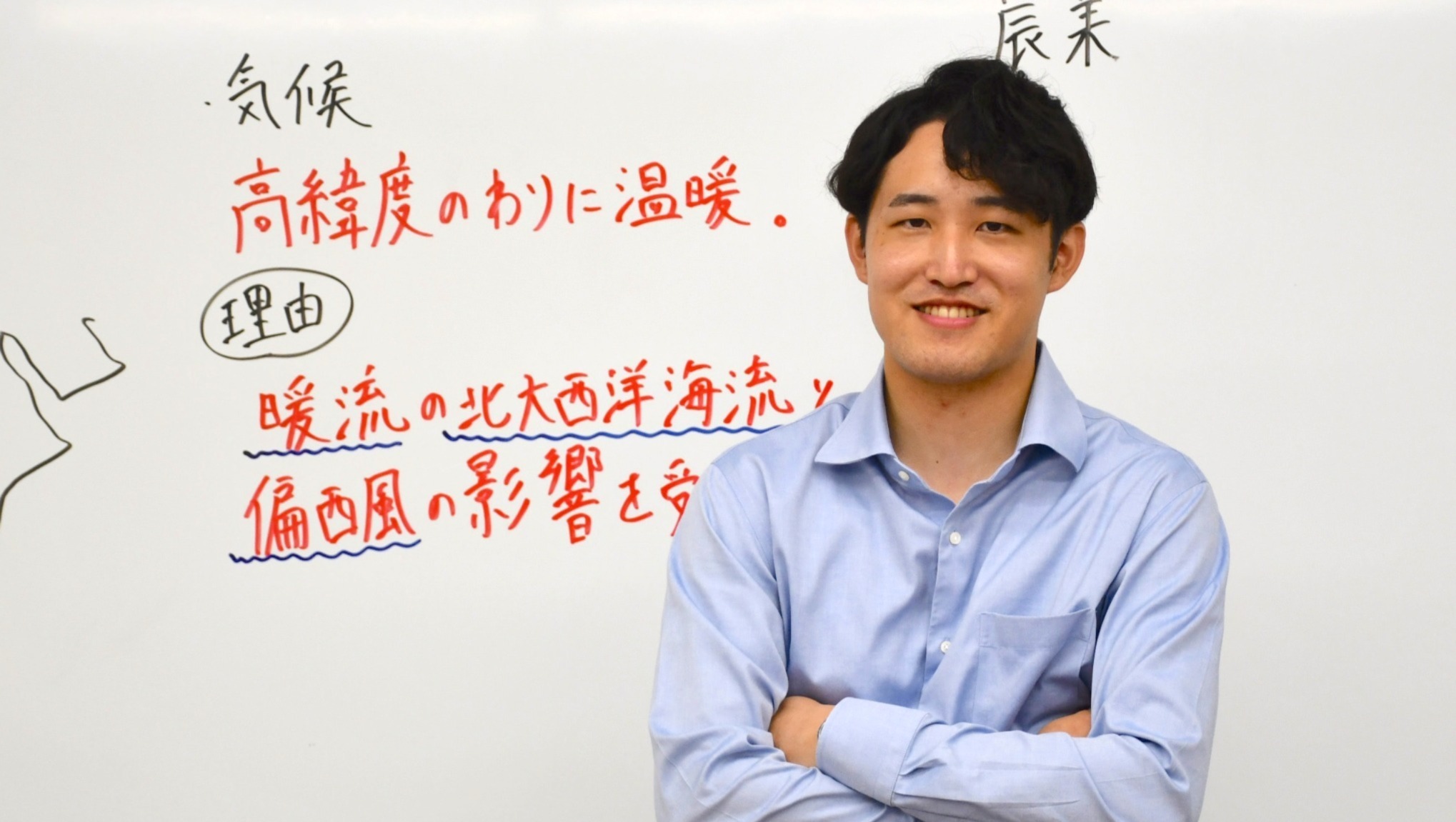誰かの人生の一助に/東進衛星予備校 石松 岳留
2025/07/15
受験期に救われた経験が、今の私の原点。
悩みながら前に進む生徒の伴走者として、真摯に寄り添います。
PROFILE

石松 岳留
2022年4月新卒入社
下関市立大学出身
東進衛星予備校スタッフ
英進館は「教育への情熱」と「自らの成長」が両立する環境
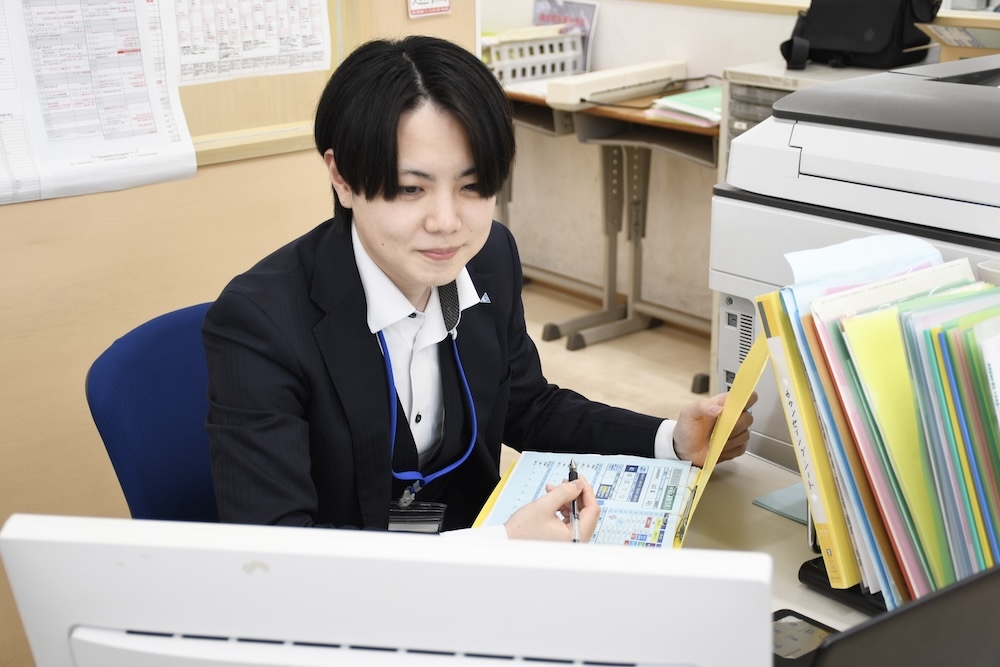
私はもともと教育に興味があり、大学時代には個別指導塾でアルバイトをしていました。目の前の生徒が少しずつ成長していく姿を見られることが大きなやりがいでした。
なかでも印象的だったのは、担当していた生徒が志望校に合格し、塾を卒業する際に「先生のおかげです」と感謝の言葉をかけてくれたことです。その瞬間、「教育の仕事に本気で向き合ってみたい」と思うようになりました。
就職活動では、教育業界はもちろん、人の成長に関わる仕事がしたいという思いから人材業界なども視野に入れていました。
そんな中で英進館に惹かれた大きな理由のひとつが、社長の教育に対する熱量です。実際に社長が授業をされている動画を見たとき、生徒一人ひとりに真摯に向き合う姿勢に心を打たれました。「この会社なら、自分も本気で生徒と向き合える」と感じたのを今でも覚えています。
また、英進館は多くの生徒に選ばれ、今なお成長を続けている勢いのある企業です。「ここなら自分自身も成長できる」という確信を持てたことも、入社を決める後押しになりました。
そして、もう一つの決め手が、私自身の高校時代の経験です。私は実際に東進衛星予備校に通っていたのですが、受験に悩んでいた時期に、担任の先生に本当に救われました。
今度は自分が生徒の力になりたい。その想いが、英進館への入社を決意させてくれました。
生徒とともに悩んで乗り越える、“伴走者”としての覚悟

仕事をしていて最も難しさを感じるのは、目の前の生徒が悩んでいる姿を見たときです。英進館にはたくさんの生徒が在籍していますが、中には成績が思うように伸びず、自信を失ってしまう子もいます。また、高校生という多感な時期だからこそ、学業以外にも人間関係の悩みを抱えていたり、時には恋愛相談を受けることもあります。
そうした悩みに向き合う中で、「もっと自分にできることがあったのではないか」と、自らの力不足を痛感する場面も多々あります。
とはいえ、落ち込んでばかりはいられません。まずは生徒の気持ちを真摯に受け止め、その上でサポートできるように切り替えます。「どうすればこの生徒がもう一度前を向けるだろうか」「自分にできることは何か」を常に考え、言葉を選びながらアドバイスをします。その結果、生徒が少しずつ元気を取り戻し、前に進む姿を見せてくれたときには心からうれしく思います。
それは「この仕事を選んで本当に良かった」と感じる瞬間であり、私自身のモチベーションを高める原動力にもなっています。
一方で、あまりにも生徒の悩みに深く入り込みすぎると、他の業務とのバランスが取れなくなることもあります。そのため、一定の心の距離は保ちつつ、ただ話を聞くだけで終わらず、必ず一緒に考え、前に進めるように寄り添うことを大切にしています。生徒の伴走者として、最後まで一緒に走り抜ける気持ちで向き合っています。
生徒の未来に関わる誇り、教育現場で得られる深い充実感
やりがいを感じる瞬間は数多くありますが、中でも一番心に残るのは、生徒が卒館していくときに「先生のおかげです」と感謝の言葉を伝えてくれたときです。
英進館の高等部には、幼稚園・小・中・高と長く通ってくださる生徒も多く、(高等部は)まさに“英進館の出口”とも言える場所です。それほど長い間、私たちを信じて努力してきてくれた生徒たちの最後の節目に立ち会えることは、何よりの喜びであり、本当にかけがえのない瞬間です。
彼らが大学を卒業し、社会に巣立ったあと、「あのとき先生が言ってくれた言葉が支えになっています」と言ってもらえることもあります。このように、少しでも記憶に残る存在でいられたなら、教育に携わる者として最高の誇りです。
高校時代は、人生においても特に多感で重要な時期です。その大切な時間に関わることができるというのは、本当に大きなやりがいですし、時として生徒の人生を良い方向に導く「道しるべ」たる存在になれる、それがこの仕事の魅力です。
さらに、生徒だけでなく、一緒に働く大学生のアルバイトスタッフたちとの関わりもやりがいのひとつです。就職を控えた大学生から、職業選択や将来の相談などを(身近な社会人の先輩として)受けることも多くあります。「英進館でのアルバイトが自分を成長させてくれた」と言ってくれる学生もいて、彼らの人生にも良い影響を与えらているのだと実感しています。
生徒、保護者、大学生のアルバイトスタッフ――さまざまな人との関わりを通じて、誰かの人生の一助となれる。それこそが、英進館で、東進衛星予備校で働くうえでの何よりのやりがいです。
寄り添い続けた1年が、感謝の言葉として返ってきた瞬間
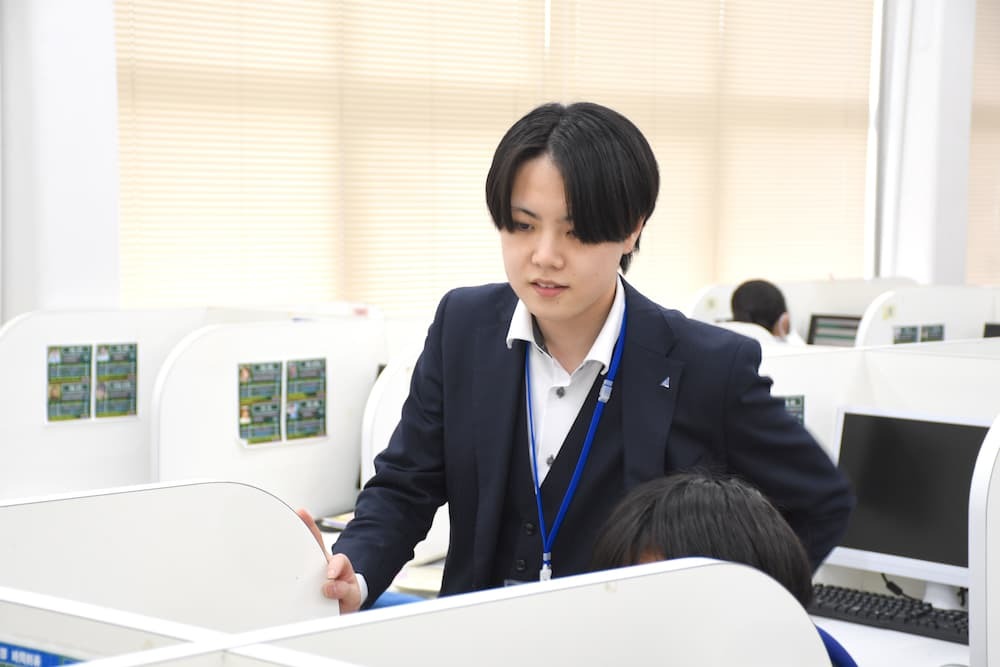
私が1年目に福岡の天神本館で担当していた(当時)高校1年生の生徒とのエピソードが特に記憶に残っています。
私が2年目以降大分校に異動した関係で、その後は直接関わる機会が減ったのですが、大学に合格したタイミングで、わざわざ私の校舎に電話をくれたんです。「あの時、先生のおかげで本当に助かりました」と感謝の気持ちを受け取って、本当に驚きましたし、嬉しかったですね。
その生徒は、高校に入学したばかりの頃、人間関係や成績、さらには将来のことまで、多くの悩みを抱えていました。特に「自分はこの先、何をしたいのかも分からない」「これから3年間やっていけるのか不安だ」と話していたのが印象的で、私もできる限り寄り添い、前向きになれるよう声をかけ続けていました。
直接的な関わりはわずか1年間でしたが、その後も私のことを記憶にとどめ、わざわざ感謝の気持ちを伝えてくれたことは、(私にとって)大きな励みとなりました。その生徒の言葉から、少なからず自分がその子の人生に関わり、影響を与えることができたのだと、教育の仕事の重みとやりがいを改めて感じました。
「ここが自分の居場所」と思ってもらえる空間づくりを大切に

仕事をする上で私が一番大切にしているのは、校舎の空気感です。学びの場ではありますが、まずは生徒が安心して通えて、自分の悩みを打ち明けられるような「居心地のよい空間」をつくることが重要だと考えています。
学力をつける大前提として、「ここは自分の居場所だ」と思ってもらえる環境でなければ、生徒も心を開いてくれませんし、継続して努力することも難しくなってしまいます。
そのために心がけていることは、まず「笑顔で生徒を迎える」ことです。生徒が来館したときには「おかえり」「今日学校どうだった?」といった声かけを積極的かつ自然にするようにしています。家庭ではなかなか話せないようなこともここでは自然と話せる、そんな空間づくりを意識しています。
下手に質問するだけでは尋問のようになってしまうので、生徒の笑顔を引き出すような話題を考えるようにしています。生徒の表情や反応を見ながら、距離感には細心の注意を払い、「ちょうどいい関わり方」を常に探っていますね。
休みの調整も自由に!プライベートも大切にできるからこそ続けられる安心感
プライベートの時間は、自分のペースでしっかりリフレッシュできています。特に私が所属している東進衛星予備校部門の場合、休みの取得もある程度自分で調整できるため、「この日に旅行に行きたい」「この週は少しゆっくりしたい」といった予定も立てやすい環境です。
私自身、旅行の予定にあわせて休みを調整したり、自宅でゆっくり過ごす日を作ったりと、無理なくプライベートも楽しめています。
私は外に出るのも、家で過ごすのもどちらも好きなタイプで、その時の気分に合わせて行動しています。今はせっかく大分に住んでいるので、ドライブがてら温泉に行くこともありますし、歌うことが好きなので、1人でカラオケに行くこともあります。
最近は花粉の季節ということもあって、家で過ごすことが多いのですが、実はつい先日プロジェクターを奮発して購入しました。さながら「おうち映画館」でして、好きな作品を観ながらのんびりする時間は最高のリフレッシュになっていますね。
英進館には、若い社員だけでなく家庭を持っている先輩方も多く、それぞれのライフスタイルに合わせてお休みを取ったり、家族との時間を大切にしておられます。そうした柔軟な働き方ができる職場環境だからこそ、長く続けられるという安心感があります。
プライベートを大切にしながら、教育の仕事に打ち込めるのは、英進館の大きな魅力のひとつだと感じています。
生徒だけでなく、仲間を支える存在へ

将来的には、現場での生徒対応だけでなく、マネジメントや運営といった部分でも貢献していきたいと考えています。校舎の運営を支え、後輩スタッフがよりのびのびと働ける環境を整えるなど、「裏方として支える立場」になっていくことが、(5年後、10年後を考えると)今後の自分の役割だと感じています。
英進館には、若い人を積極的に育て、活躍のチャンスを与えてくれる風土があります。私自身も、入社してから多くの機会をいただいてきました。今後はそのたすきを次の世代につないでいきたいと思っています。
これから新しく入ってくる後輩スタッフが、「生徒に本気で向き合えるような職場」を作っていくことが、私の責務です。そのために、今は自分自身がまずしっかりと力をつけて、(校舎長として)独り立ちし、周りを支えられる存在になりたいです。
そしていつか、私が担当していた生徒が「今度は自分が英進館で生徒を支えたい」と言ってスタッフとして入社してくれるような、そんな循環が生まれたら嬉しいですね。そのような後輩が安心して働ける環境をつくることも、これからの私の大切な目標です。